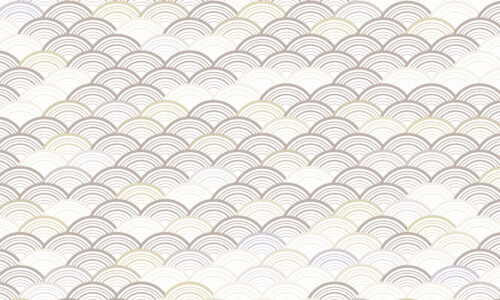(募集終了)【久留米市】大善寺玉垂宮の鬼夜(2026年1月)
2026年1月7日 〜 2026年1月7日
- 久留米
- 冬
- ちから仕事
- 行事参加
「大善寺玉垂宮の鬼夜」は、大晦日の夜から正月7日まで行われる「鬼会(オニエ)」の最終日に行われる行事で、1600年余りの伝統があり、日本三大火祭りの一つに数えられるとともに、国の重要無形民俗文化財に指定されています。日本一といわれる大松明6本が紅蓮の炎を上げて燃え盛り、それを数百人の裸の氏子若衆がカリマタで支えて境内を廻るという熱気あふれる勇敢な年頭の祭りです。この大松明の火をあびると無病息災といわれ、家内安全、災難消除、開運招福を祈願されるかたで賑わいます。1月4日午前中に大松明を作り、奉納します。(松明):長さ13メートル、頭部の径1メートル、重さ約1.2トン、6本◎祭りの流れ19:00頃境内参集19:30頃お汐井かき21:30頃大松明点火、鉾面神事、松明廻し22:00頃鬼の禊(汐井場での火消し)23:00頃行事終了

(募集終了)【飯塚市】大分八幡宮 放生会(2025年9月)
2025年9月28日 〜 2025年9月28日
- 筑豊
- 秋
- ちから仕事
- 当日運営補助
- 行事参加
放生会として知られる秋の例大祭は、9月の最終土曜日と日曜日に斎行されています。土曜日に祭座・獅子舞を、日曜日は祭典・獅子舞・流鏑馬・餅まき・御神幸祭が執り行われています。八幡大神と縁の深い放生会は、もともと仏教の教えに基づくもので、魚や鳥など生き物を放つ法会に由来します。八幡宮では、養老4年(720)に宇佐にて、八幡大神の託宣による放生が行われたのがその始まりとされています。大分八幡宮で放生会が始まったのがいつかは定かではありませんが、宇佐神宮の創建された神亀2年(725)の翌年の神亀3年(726)が創建であることから、当初から放生会は執り行われていたと考えられています。また、記録としては昌泰3年(900)に太政官符により官幣に預かった際に、放生会が斎行されたと記されています。応仁の乱以降の衰退により放生会は途絶えますが、享保6年(1721)8月15日に復活しました。享保8年(1723)には「流鏑馬」が、その翌年の享保9年(1724)には村人が石清水八幡宮で習得してきた「獅子舞」が奉納され、享保15年(1730)には「御神幸祭」が再開され、神事祭事が整えられることとなりました。明治期の神仏分離の後しばらくは、「仲秋祭」と名を変えていましたが、現在は「放生会」に改められています。日曜日の御神幸祭で神霊が御乗りになられる神輿は、享保9年(1724)3月に、庄屋の伊佐甚九郎直友、伊佐市郎治直伝、伊佐藤五郎によって寄進されたことが墨書されています。また、放生会の中で奉納される獅子舞では、かすかに憂いを含みながらも賑やかな、笛と太鼓と銅拍子の囃子の調子の緩急に合わせ、二頭の獅子が一対となって舞い踊っています。享保の昔から変わらず受け継がれてきた獅子舞は、古式をよく伝え、筑前地方の他の獅子舞に与えた影響も大きいことから、福岡県指定無形民俗文化財となっています。(詳細については、大分八幡宮HP(https://www.daibu-hachiman.com/hojoe.html)をご確認ください。)

(募集終了)【北九州市】小倉祇園祭 平松の神輿(2025年7月)
2025年7月19日 〜 2025年7月19日
- 北九州
- 夏
- ちから仕事
- 行事参加
(※今年は土曜日の開催です!)平松御神輿は、細川忠興が400年前(1618年)に小倉城を築城したときに八坂神社に奉納した御神輿であり、北九州市小倉北区平松町に江戸時代から代々受け継がれてきた、由緒ある御神輿です。小倉祇園では、大漁、五穀豊穣、無病息災、家内安全を祈願して、先祖代々受け継がれて来た口説き(くどき)に合わせて約100名が交代で担ぎ、太鼓競演会の露払いとして勇壮な練りを披露します。現在、平松御神輿は唯一の神輿として小倉祇園に参加し続けています。小倉祇園といえば現在は「太鼓山車」のイメージですが、平松御神輿は江戸~明治にかけて町方が行ってきた「廻り祇園」の形態を残しており、かつての廻り祇園の伝統文化を現在に継承している大変貴重な文化財です。平成22年には、北九州市の無形民俗文化財に指定されています。(参考)Youtubeで「平松神輿アーカイブ」で検索していただくと、行事の様子を動画で確認することができます!「平松御神輿祭実行委員会Youtube」

(募集終了)【糸田町】糸田祇園山笠(宮床行政区子ども山笠)(2025年5月)
2025年5月10日 〜 2025年5月11日
- 筑豊
- 春
- ちから仕事
- 行事参加
300年以上続く伝統行事で、各地区が高さ最大で9m、重さ2トン以上の飾り山笠を担ぎ、町内を練り歩く勇壮な祭りです。1日目:15時より貴船神社にて神事(お祓い)を行い出発。18時前まで地域内を周回します。(20~30分おきに御旅所にて休憩あり)2日目:12時30分公民館にて出発の神事を行い、地域内を周回します。
_250228_1-500x300.jpg)
(募集終了)【豊前市】古式春季神幸大祭(八屋祇園)(2025年4月)
2025年4月29日 〜 2025年5月1日
- 北九州
- 春
- ちから仕事
- 行事参加
- その他
3基の神輿に7台の山車(大舟、山鉾、踊車)が続き、地域氏子総出にて繰り広げられる壮大なお祭りです。4月29日には汐かき・町内巡幸、4月30日は「お下り(おくだり)」が行われ、お神様を御神輿で御旅所にお運びします。氏子地域各所をお神様が神幸することで、地域の安寧を祈るのです。御神輿は御旅所にて一夜を過ごされたのち、翌5月1日に大富神社へ戻ります。特に4月30日夕からは御神輿が御旅所に到着し、各山車がそれに引き続いて到着し始めるころ、祭りは最高潮に達し御旅所は多くの人で賑わいます。(参考)「八屋祇園公式HP」

(募集終了)【田川市】風治八幡宮例大祭川渡り神幸祭(2025年5月)
2025年5月17日 〜 2025年5月18日
- 筑豊
- 春
- ちから仕事
- 企画調整
- 当日運営補助
その歴史は古く、永禄年間疫病流行の際に、氏子一同悪疫平癒を祈願し、御願成就の御礼として、山笠を建立し神幸祭に奉仕したことに始まると伝えられます。運行する神輿としては日本最大級の大神輿が、五色のバレンで飾り立てた十台余の幟山笠を引具して、彦山川の川瀬を練り渡る勇壮にして豪壮な一大神事です。山笠には何れも長い綱をつけて子供が曳き、舵棒や屋台には若衆が付き、いなせな采配振りが台上から号笛など吹いて彦山川の清流を押し渡り、祭り囃しは町内隈無く響き渡り、新緑に包まれた大川筋一帯を祭り一色に染め上げます。福岡県指定無形民俗文化財第一号に指定され、県五大祭りの一つに数えられる絢爛豪華な一大絵巻です。(参考)「風治八幡宮川渡り神幸祭2023PV~」

(募集終了)【久留米市】大善寺玉垂宮の鬼夜(2025年1月)
2025年1月7日 〜 2025年1月7日
- 筑後
- 冬
- ちから仕事
- 行事参加
「大善寺玉垂宮の鬼夜」は、大晦日の夜から正月7日まで行われる「鬼会(オニエ)」の最終日に行われる行事で、1600年余りの伝統があり、日本三大火祭りの一つに数えられるとともに、国の重要無形民俗文化財に指定されています。日本一といわれる大松明6本が紅蓮の炎を上げて燃え盛り、それを数百人の裸の氏子若衆がカリマタで支えて境内を廻るという熱気あふれる勇敢な年頭の祭りです。この大松明の火をあびると無病息災といわれ、家内安全、災難消除、開運招福を祈願されるかたで賑わいます。1月4日午前中に大松明を作り、奉納します。(松明):長さ13メートル、頭部の径1メートル、重さ約1.2トン、6本◎祭りの流れ19:00頃境内参集19:30頃お汐井かき21:30頃大松明点火、鉾面神事、松明廻し22:00頃鬼の禊(汐井場での火消し)23:00頃行事終了

(募集終了)【飯塚市】大分八幡宮 放生会(2024年9月)
2024年9月29日 〜 2024年9月29日
- 筑豊
- 秋
- ちから仕事
- 当日運営補助
- 行事参加
八幡大神と縁の深い放生会は、もともと仏教の教えに基づくもので、魚や鳥など生き物を放つ法会に由来します。八幡宮では、養老4年(720)に宇佐にて、八幡大神の託宣による放生が行われたのがその始まりとされています。大分八幡宮で放生会が始まったのがいつかは定かではありませんが、宇佐神宮の創建された神亀2年(725)の翌年の神亀3年(726)が創建であることから、当初から放生会は執り行われていたと考えられています。また、記録としては昌泰3年(900)に太政官符により官幣に預かった際に放生会が斎行されたと記されています。応仁の乱以降の衰退により放生会は途絶えますが、享保6年(1721)8月15日に復活。享保8年(1723)には流鏑馬。その翌年の享保9年(1724)には村人が石清水八幡宮で習得してきた獅子舞が奉納され、享保15年(1730)には御神幸祭が再開され、神事祭事が整えられることとなりました。明治期の神仏分離の後しばらくは、仲秋祭と名を変えていましたが、現在は放生会に改められています。日曜日の御神幸祭で神霊が御乗りになられる神輿は、享保9年(1724)3月に、庄屋の伊佐甚九郎直友、伊佐市郎治直伝、伊佐藤五郎によって寄進されたことが墨書されています。また、放生会の中で奉納される獅子舞は、筑前地方の他の獅子舞に与えた影響も大きいことから、福岡県指定無形民俗文化財となっています。

(募集終了)【北九州市】小倉祇園祭 平松の神輿(2024年7月)
2024年7月21日 〜 2024年7月21日
- 北九州
- 夏
- ちから仕事
- 行事参加
平松御神輿は、細川忠興が400年前、1618年に小倉城を築城したときに八坂神社に奉納した御神輿であり、大変歴史のある御神輿で、平成22年に北九州市民俗文化財に指定されました。先祖代々受け継がれて来た口説き(くどき)に合わせて約100名が交代で担ぎねり歩きます。かつての廻り祇園の伝統文化を現在に継承している大変貴重な文化財です。大正から昭和にかけて、その「廻り祇園」が消滅し、祇園祭は「太鼓祇園」化していきましたが、平松御神輿は唯一の神輿として小倉祇園に参加し続けています。(参考)「平松御神輿祭実行委員会Youtube」

(募集終了)【芦屋町】八朔の節句(2024年9月)
2024年5月8日 〜 2024年9月22日
- 北九州
- 夏
- ちから仕事
- 事前準備
- 当日運営補助
芦屋町では、約300年前から伝わる「八朔の節句」という伝統行事が今も続いています。この節句は、長男が生まれ、初めて迎える八朔(旧暦の8月1日。現在の9月1日)の時にわら馬(八朔の馬)を、長女の場合は団子雛(だごびーな)を飾り、わが子の健やかな成長を祈願する行事です。

(募集終了)【田川市】風治八幡宮例大祭川渡り神幸祭(2024年5月)
2024年5月18日 〜 2024年5月19日
- 筑豊
- 春
- ちから仕事
- 企画調整
- 当日運営補助
その歴史は古く、永禄年間疫病流行の際に、氏子一同悪疫平癒を祈願し、御願成就の御礼として、山笠を建立し神幸祭に奉仕したことに始まると伝えられます。運行する神輿としては日本最大級の大神輿が、五色のバレンで飾り立てた十台余の幟山笠を引具して、彦山川の川瀬を練り渡る勇壮にして豪壮な一大神事です。山笠には何れも長い綱をつけて子供が曳き、舵棒や屋台には若衆が付き、いなせな采配振りが台上から号笛など吹いて彦山川の清流を押し渡り、祭り囃しは町内隈無く響き渡り、新緑に包まれた大川筋一帯を祭り一色に染め上げます。福岡県指定無形民俗文化財第一号に指定され、県五大祭りの一つに数えられる絢爛豪華な一大絵巻です。(参考)「風治八幡宮川渡り神幸祭2023PV~」

(募集終了)【上毛町】松尾山のお田植祀(2024年4月)
2024年4月14日 〜 2024年4月14日
- 北九州
- 春
- ちから仕事
- 当日運営補助
八百年も前から続いている伝統行事で、一年間の稲作作業のすべてをまねて奉納しその年の豊作を祈る祭りです。松尾山のお田植祭は田行事として水留め(みずとめ)、畦塗り(あぜぬり)、田打ち(たうち)、代(しろ)かき、種子蒔き(たねまき)、田植え(たうえ)の6つの演目に、色衆楽(いろしのがく)とよばれる楽打ちを加えた7つの演目から構成されています。色衆楽は中世の田楽が起源と考えられます。横笛の囃子に合わせて、締太鼓やビンササラと呼ばれる拍子板を打ち鳴らしながら踊ります。近年、保存会により長刀舞(なぎなたのまい)と鉞舞(まさかりまい)とよばれる刀行事や獅子舞が復興され、往年の松会行事に近づきつつあります。長刀の舞は鎌倉時代から室町時代にかけて、武装していた山伏たちの主要であった長刀が、松会に使用され祭器となりました。長刀を振り回すことが魔物を払う意味を持つと言われ、天下泰平を祈ります。

(募集終了)【久留米市】大善寺玉垂宮の鬼夜(2024年1月)
2024年1月7日 〜 2024年1月7日
- 筑後
- 冬
- ちから仕事
- 行事参加
「大善寺玉垂宮の鬼夜」は、大晦日の夜から正月7日まで行われる「鬼会(オニエ)」の最終日に行われる行事で、1600年余りの伝統があり、日本三大火祭りの一つに数えられるとともに、国の重要無形民俗文化財に指定されています。日本一といわれる大松明6本が紅蓮の炎を上げて燃え盛り、それを数百人の裸の氏子若衆がカリマタで支えて境内を廻るという熱気あふれる勇敢な年頭の祭りです。この大松明の火をあびると無病息災といわれ、家内安全、災難消除、開運招福を祈願されるかたで賑わいます。1月4日午前中に大松明を作り、奉納します。(松明):長さ13メートル、頭部の径1メートル、重さ1.2トン、6本◎祭りの流れ19:00頃境内参集20:00頃お汐井かき21:30頃大松明点火、鉾面神事、松明廻し22:00頃鬼の禊(汐井場での火消し)23:00頃行事終了

(募集終了)【筑後市】熊野神社鬼の修正会(2024年1月)
2024年1月6日 〜 2024年1月6日
- 筑後
- 冬
- ちから仕事
- 行事参加
「追儺(ついな)祭(さい)」ともいわれ、約500年前に無病息災を祈願する火祭りとして始まった祭りです。修正会(しゅじょうえ)とは、毎年正月初めに仏に罪過をざんげして国の安泰や五穀豊穣などを祈る法会のことです。鬼の修生会は、坂東寺創建(延暦年中約1250年前)と同時に無病息災を祈願する火祭りとして始められ、鬼追いの儀式が今に伝わっています。(福岡県指定無形民俗文化財S44.10.20)行事は子供による「小松明(17:00~18:00)」、鬼の面をつけた宮司を追い立てる「鬼追い」、さらしとふんどし姿の氏子により行われる「大松明(21:00~22:30)」の3つで構成されています。16時になると360人程の子供たちが集まり、それぞれの小松明に火を灯して神殿を巡回し、21時頃になると締め込み姿の男衆が、燃え盛る3本の大松明(直径1.5m、長さ15m)を「刈又」と呼ばれる棒で支え、「ワッショイ、ワッショイ」の掛け声で境内を巡回します。(参考)平成29年「熊野神社鬼の修正会~追儺祭(鬼夜)~」